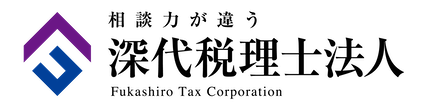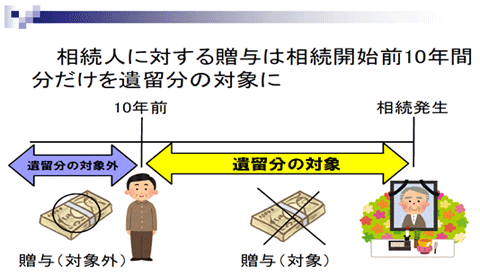
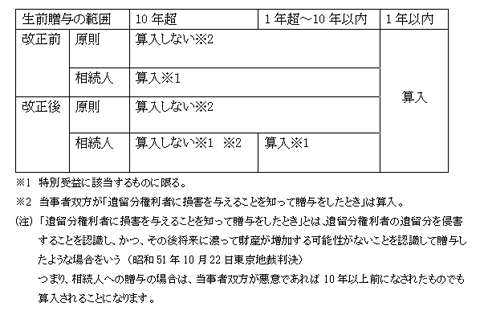
民法第1044条(遺留分の計算の基準となる贈与)
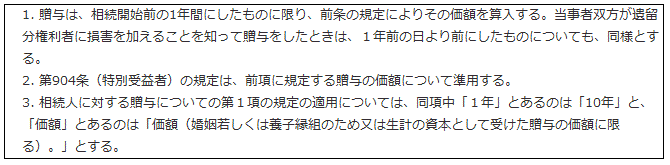
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
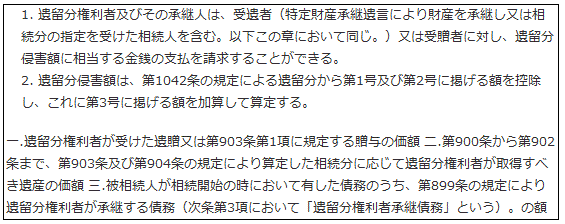
遺留分侵害額=(遺留分の額)-(遺留分権利者が受けた特別受益の額903条①)-(遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む)には具体的相続分に応じて取得すべき遺産の額(ただし、寄与分による修正は考慮しない))+(899条の規定により遺留分権利者が承継する相続債務の額)
中小企業の事業承継に関わる民法(相続法)の見直しのポイント
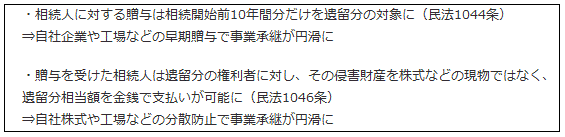
事業承継対策がしやすくなった
- 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に発生することを回避することができる。
- 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたという遺言者の意思を尊重することができる。
- 受遺者または受贈者は、遺留分侵害額の請求に対し、現物による返還を選択することはできない。
遺留分の法的性質の見直し
- 「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」になった。
- 遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の 支払いを請求することができる(民法1046①)
⇒物権的効力から債権的効力に変更された。⇒金銭債権化 ⇒譲渡税が課税。
【所得税基本通達33-1の6】 金銭以外は譲渡課税
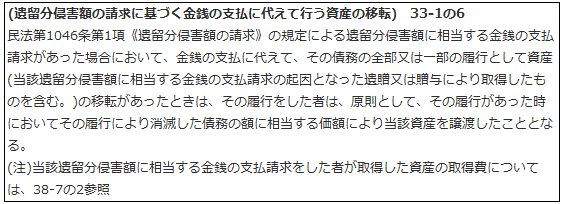
【所得税基本通達38-7の2】 不動産の場合の取得費の金額
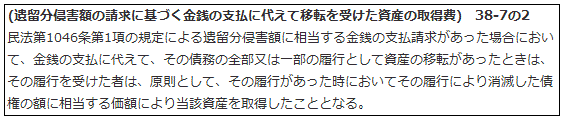
本ページに掲載した画像は情報サイト相続.co.jp様より転載許可を得て掲載しています。