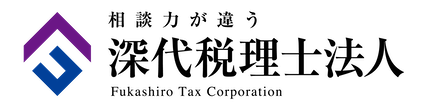今回は、配偶者居住権の具体的な計算を行っていきます。
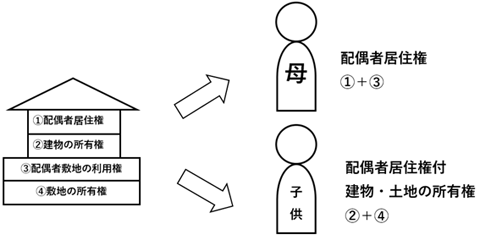
1.建物の評価
① 配偶者が取得した配偶者居住権建物の固定資産税評価額-②
② 子供が取得した配偶者居住権付建物の所有権
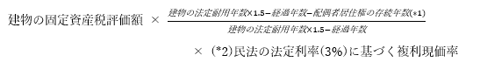
*1 配偶者居住権の存続年数
配偶者居住権の存続年数とは、配偶者が終身まで居住権を使用する年数すなわち相続開始時における配偶者の平均余命年数。
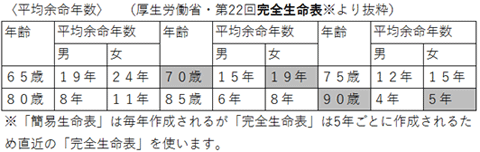
*2 民法の法定利率に基づく複利現価率
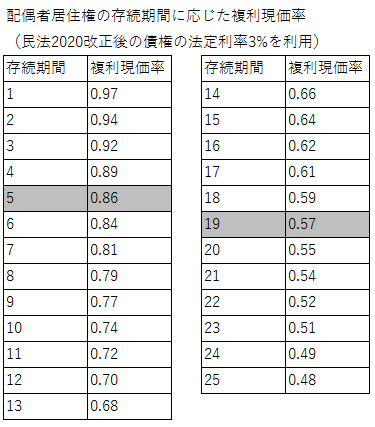
2.土地の評価
③ 配偶者が取得した配偶者居住権に基づく敷地利用権土地の相続税評価額-④
④ 子供が取得した配偶者居住権付敷地の価額
相続税評価額 × 民法の法定利率(3%)に基づく複利現価率
3.具体的な計算
事例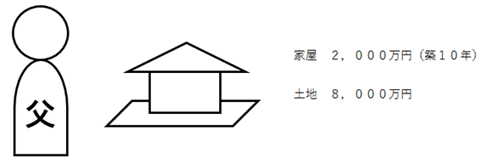
ケース1.配偶者が70歳の場合
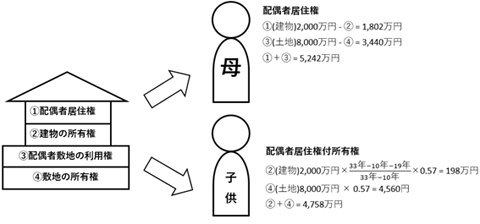
ケース2.配偶者が90歳の場合
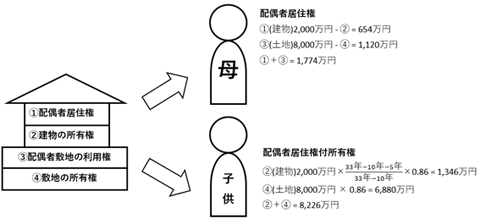
ケース1とケース2の違いは、配偶者の年齢が70歳か90歳かの違いのみですが、平均余命によって配偶者居住権の額が大きく異なっています。
70歳の場合の建物利用権に基づく評価額が固定資産税評価額に近くなっていて、配偶者居住権をなるべく低くしたいとする立法趣旨からすると高いです。
しかし、敷地利用権の評価が低く評価されていますので、配偶者居住権の5,242万円は不動産全体1億円のおおよそ50%ですから立法趣旨に近い評価になっていると思います。
4.小規模宅地等の評価減と配偶者居住権
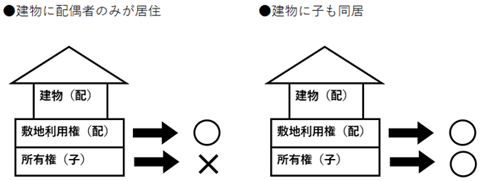
特例の要件を満たせば、配偶者居住権に基づく敷地利用権(母)と配偶者居住権付敷地の価額(=配偶者居住権付所有権)(子)とも小規模宅地の特例の特例が認められます。
5.二次相続では配偶者居住権は非課税に
配偶者居住権を取得後に配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅します。配偶者居住権が消滅すれば子供の建物・敷地の所有権は完全な所有権を得ることになりますが、これは配偶者からの財産の取得ではありませんので、相続税は課税されません。
しかし、配偶者が生きている間に配偶者居住権が移動した場合には、価値がありますので、贈与税が課税されます。
本ページに掲載した画像は情報サイト相続.co.jp様より転載許可を得て掲載しています。